
目次
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材の採用で最も一般的な在留資格ですが、少なくとも一定の専門性のある業務をメインとして担当してもらう必要があります。
ここでは、採用する人材に必要な許可が技人国ビザで問題ないか確かめられるよう、できる業務・できない業務を具体例を交えて解説します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)は、専門的なスキルや知識を持つ外国人が日本で働く際に最も一般的に利用される就労ビザのひとつです。このビザは、従事する業務内容によって大きく3つの分野に分類されます。それぞれの分野でどのような業務が許可されるのか、その定義と具体的な業務例を理解することが、適切な人材配置とビザ申請の第一歩となります。自社で採用したい外国人の業務が、これらのどの分野に該当するのかを確認していきましょう。
理学、工学、農学、医学、薬学といった自然科学の分野に属する学術的な知識を必要とする専門業務が対象です。大学や専門学校で修得した体系的な知識を背景とした、一定水準以上の専門性が求められます。具体的な職務としては、以下のようなものが挙げられます。
| 設計・開発 | ソフトウェア、アプリケーション、機械、電気回路などの設計や開発業務 |
| システム解析・検査 | CADやCAEを用いたシステム解析、製品の総合試験や品質検査 |
| プログラミング | システムエンジニアやプログラマーとしての開発・構築業務 |
| 研究開発 | 食品会社やメーカーにおける新製品の研究や技術開発 |
法律学、経済学、社会学、経営学、商学、教育学といった人文科学の分野に関する知識を必要とする専門業務がこの分野に該当します。自然科学分野と同様に、学術的な素養を背景とした専門的な判断が求められる業務である必要があります。代表的な職務は以下のとおりです。
| 会計・経理 | 企業の海外事業部門における貿易関連の会計処理 |
| 法務補助 | 法律事務所における弁護士の補助業務 |
| コンサルティング | IT企業や経営コンサルティングファームにおける専門的助言 |
| マーケティング・市場調査 | 海外市場の動向調査や販売管理、需給管理 |
| 貿易実務 | 商社などにおける海外企業との取引や書類作成 |
この分野の業務は、外国の文化に根差した考え方や感受性を必要とすることが特徴です。単に外国人であるというだけでなく、日本人にはない発想や感覚を活かした、一定水準以上の専門能力が求められます。大学を卒業した人が翻訳・通訳、語学指導に従事する場合を除き、原則として3年以上の関連業務での実務経験が必要です。
| 翻訳・通訳 | 海外企業との契約書翻訳や、商談での通訳など |
| 語学の指導 | 企業内の語学研修の講師など |
| 広報・宣伝 | 外国人向けウェブサイトの作成や、海外メディア向けのPR活動 |
| 海外取引 | 海外の取引先との連絡調整や、現地販売店との連携強化 |
| デザイン | 外国特有の文化を反映した服飾や室内装飾のデザイン |
| 商品開発 | 海外市場のニーズに基づいた新商品の企画立案 |
技人国ビザは多くの専門職で活用できますが、どのような業務でも許可されるわけではありません。特に、専門性を必要としないと見なされる活動は厳しく制限されています。採用後のミスマッチやビザの不許可といったコンプライアンス上のリスクを避けるため、許可されない業務の範囲を正確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、代表的なNGパターンを2つ解説します。
技人国ビザで許可される活動は、学術的な素養を背景とした「一定水準以上の専門性」を持つ業務に限られます。そのため、誰でも短期間の訓練で習得できるような単純作業に従事させることはできません。
たとえば、以下のような現場作業は、専門性や学術的知識が不要と判断されるため原則として認められません。
また、専門分野に関連しているように見えても、主体的な創作活動や分析、専門的な判断を伴わない補助的な作業だけを任せることも不適切です。アニメ制作会社で背景の色付けだけを担当したり、服飾メーカーで裁断や縫製といった制作工程のみに従事させたりするケースは、専門性を発揮しているとは見なされず、許可されにくいでしょう。
「研修」という名目であっても注意が必要です。日本人社員と同様のキャリアステップの一環として、将来の専門業務に不可欠な現場経験を短期間積むことは許容されます。しかし、その実態が非該当業務であり、在留期間の大半を占めるような研修計画は、実質的な単純労働と判断され、不許可となるリスクが極めて高くなります。
契約書や職務内容説明書に専門業務が記載されていても、実際の活動のごく一部に過ぎず、その大半が専門性を要しない業務である場合、全体として「技人国ビザに該当しない」と判断される可能性があります。例えば、通訳として採用したにもかかわらず、実際にはほとんどの時間を店舗での接客販売や商品陳列に費やしているようなケースです。
もちろん、業務の都合上、一時的に荷物を運んだり、応援で簡単な作業を手伝ったりすることまでが、直ちに問題視されるわけではありません。しかし、そのような非該当業務が常態化し、結果的に主たる活動となってしまった場合、在留期間の更新時に不許可と判断される恐れがあります。
このような事態を避けるためには、採用段階で専門業務が主たる活動となるような配属設計が重要です。複数の業務を兼務させる場合は、それぞれの業務の比率を管理し、日報や週次報告などで専門業務が中心であることを客観的に示せるように記録を残しておくことが、リスク管理の観点から有効な対策となります。
すでに説明しましたが、技人国ビザで許可されるのは、学術的な知識や専門的なスキルを活かす業務です。技人国ビザでできる業務の具体例を挙げると、次のとおりです。
■IT分野
……ソフトウェアの設計・開発、プログラミング、CAD/CAEシステムを用いた解析やテクニカルサポートなど
■商社やメーカー
……経理・会計、法律事務所での法務補助、経営コンサルティング、海外向けのマーケティング調査や貿易実務など
■外国人ならではの語学力が求められる国際業務
……海外取引先との商談における通訳、契約書の翻訳、社内での語学指導、外国人客への多言語対応を行うフロント業務など
■外国人ならではの視点が求められる国際業務
……外国人向けサービスの広報・宣伝、外国の文化やトレンドを反映した商品開発、服飾やインテリアのデザイン、海外向け広報、インバウンド向けの宿泊プラン企画など
技人国ビザの取得には、従事する業務内容だけでなく、採用する外国人本人と企業が結ぶ雇用契約の内容も厳しく審査されます。学歴と職務の関連性や報酬の水準など、以下の項目を事前に確認しましょう。
技人国ビザの審査では、本人の学歴とこれから従事する業務内容の関連性が非常に重視されます。この判断基準は、最終学歴によって扱いが異なります。
日本または海外の大学や日本の高等専門学校(高専)を卒業した人については、教育機関の特性上、幅広い知識や応用能力を身につけていると見なされるため、専攻科目と職務の関連性は比較的柔軟に判断されます。
例として、工学部出身者がコンサルティング業務に就くなど「一見して直接的でない組み合わせ」が挙げられるでしょう。
日本の専門学校を卒業した人(「専門士」または「高度専門士」の称号が必要)の場合は、職業に直結した能力を育成する機関と位置づけられているため、原則として専攻科目と職務のあいだに「相当程度の関連性」が求められます。この関連性は、成績証明書やシラバス(履修案内)、制作物などを用いて客観的に証明する必要があります。
ただし、関連性が認められる業務に3年程度従事した後は、その後のキャリアチェンジにおける職務との関連性判断は職務経歴も考慮され柔軟になる傾向があります。
専門学校卒業者のうち、文部科学大臣による「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定(令和5年文部科学省告示第53号)を受けた学科の修了者については、特例が設けられています。
この認定制度は、企業と連携した実習や日本社会への理解を深める教育が充実しているなど、質の高い教育が保証されていることを前提としています。そのため、この認定課程を修了した外国人材は、習得した知識を応用する能力が高いと評価され、専攻科目と職務内容の関連性が大学卒業者と同様に柔軟に判断されます。さらに高度専門士が付与された外国人はより職務範囲がメインの職務内容と関連する単純作業までできる在留資格特定活動46号への変更が可能になります。
※参考:https://www.mext.go.jp/content/20240417-mxt_syogai01-000034602-1.pdf
特例適用を希望して技人国ビザの許可を申請するときには、認定学科の修了証明書や成績証明書、実習内容がわかる資料などが必要です。
また、一部のファッションデザイン教育機関の特定のコース卒業者については、専門学校卒業者に求められる上陸許可基準の一部が免除される特例もあります。
学歴要件を満たせない場合でも、まだ可能性はあります。一定期間の関連する実務経験の有無です。この要件も業務分野によって異なります。
従事しようとする業務について10年以上の実務経験があれば、学歴要件の代替とすることができます。この期間には、大学や専門学校で関連科目を専攻した期間も通算できます。
翻訳、通訳、語学指導、広報、デザインといった国際業務では、原則として3年以上の関連業務での実務経験が必要です。ただし、大学卒業者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合に限り、この実務経験は不要です。ここでの「関連業務」とは、必ずしも全く同じ職務である必要はなく、関連性が認められれば複数の職務経験を通算することが可能です。
技人国ビザの外国人材に支払う報酬は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」でなくてはなりません。
報酬の比較は、同じ職務内容、学歴、社内等級、新卒・中途といった入社区分が同じ日本人社員を基準に行われます。比較対象となる日本人社員がいない場合は、同業他社の同水準の職務の求人票などを参考に、妥当な報酬額であることを説明する必要があります。
なお、ここでいう「報酬」とは、基本給や諸手当など、役務の対価として支払われるものを指します。通勤手当、扶養手当、住宅手当といった実費弁償的な手当は、原則として報酬に含まれません(ただし、課税対象となる手当は報酬と見なされる場合があります)
雇用契約は、特定のプロジェクトだけといった短期的なものではなく、安定的かつ継続的なものであることが求められます。審査では、会社の事業内容や財務状況から、継続的に業務量があり、安定して報酬を支払い続けることができるかが確認されます。
採用初期に研修を行う場合は、その研修が将来の専門業務に不可欠であることを示した上で、研修後の配属先やキャリアステップを具体的に計画書として提示しなければなりません。
技人国ビザの申請は、提出された書類に基づいて個別に審査されます。しかし、過去の事例を分析すると、許可・不許可の判断には一定の傾向が見られます。
ここでは、どのようなケースが「許可」されやすく、どのようなケースが「不許可」と判断されがちか、より具体的な事例を交えて解説します。
許可されるケースは、本人の専門性と職務内容が明確に結びついており、その必要性が客観的に説明できるという共通点があります。
本人の学歴(専攻)や職歴と、採用後の職務内容が強く関連していることは、許可を得るための最も基本的な要件です。
【例1】本国の大学で工学を専攻し、ゲームメーカーでの開発経験を持つ人が、日本のゲーム会社の開発担当としてシステムの設計やテストに従事する(月給約25万円)
【例2】日本の法学部を卒業した留学生が、法律事務所で弁護士の補助業務(法的文書の作成や調査など)に従事する
総合職として採用され、将来の幹部候補として専門業務に従事することが前提であれば、入社初期の現場研修も認められます。
【例】文学部を卒業した留学生が食品会社の総合職として採用され、日本人新卒と同様に最初の2年間は店舗で接客や商品陳列を経験し、その後本社の営業部門や海外事業部に配属される
単なる接客ではなく、語学力や異文化理解を活かす業務であれば許可の可能性は高まります。
【例1】携帯電話ショップであっても、外国人客が多い店舗で通訳を交えた販売や契約サポートを主業務とする
【例2】旅館において、フロントでの通訳業務のほか、海外の旅行会社との交渉や、外国人向けSNSでの広報活動を担う
不許可となるケースは、「専門性の要件を満たしていない」と判断されるか、申請内容の信憑性に疑義が生じる場合に大別されます。
従事する業務が、学歴や専門知識がなくとも反復訓練で習得可能と判断される場合は不許可となります。例を挙げると、次のとおりです。
申請する職務について、その必要性や業務量が客観的に見て乏しいと判断される場合は許可されません。
【例1】飲食店で「通訳」として申請したが、外国人が来ることはまれで、大半は日本人相手の接客。また注文を簡単な英語で取る・メニューを翻訳するといった業務しかしない
【例2】業務内容を「コンピュータによる会計・労務管理」としたが、実際には単純な入力やタイムカードの管理しかしない
日本人と同種の業務に従事するにもかかわらず、合理的な理由なく日本人より低い報酬が設定されている場合は不許可の原因となります。
ほかに不許可の理由となるのは、本人の素行に問題がある場合です。具体的には、留学生時代の出席率が著しく低い、あるいは資格外活動(アルバイト)の上限時間を大幅に超えて就労していたといった理由で技人国ビザの許可が下りないことがあります。
技人国ビザの就労制限でよくある質問
技人国ビザは専門知識を活かすための在留資格ですが、その運用、特に「どこまでが許可される業務範囲か」という点では疑問が生じがちです。特に、採用初期の「研修」や、業務の都合で発生する「一時的な業務内容の変更」は、多くの企業が判断に迷うポイントです。ここでは、出入国在留管理庁が示す公式ガイドラインに基づき、これらのよくある質問に回答します。
A. 専門業務とは異なる内容(例:店舗での接客、工場のライン作業など)を含む研修やOJTも、以下の条件を満たすことで許容される場合があります。注意したいのは、研修またはOJT期間から雇用が始まる場合、付与される在留期間は原則1年となる点です。
A. 一時的に専門業務ではない作業(非該当業務)に従事したからといって、直ちに在留資格違反となるわけではありません。しかし、その状態が常態化し、結果的に非該当業務が「主たる活動」になってしまうと、在留期間の更新時に不許可となるリスクが高まります。
※参考:【統合版】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁/2025年8月31日時点)
まとめ
技人国ビザを適切に運用する鍵は、①業務の専門性、②学歴・職歴との関連性、③日本人と同等の報酬水準という3つの要件を常に意識することです。採用候補者がこれらの基準を満たすか、契約内容や配属計画は妥当か、事前のチェックが欠かせません。本記事で解説したポイントを押さえ、リスクのない外国人雇用を実現してください。
個別のケースでの判断に迷う場合や、複雑なビザ申請手続きに不安を感じる場合は、専門家への相談が最も確実な解決策です。豊富な実績を持つ行政書士法人Luxentでは、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供しています。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
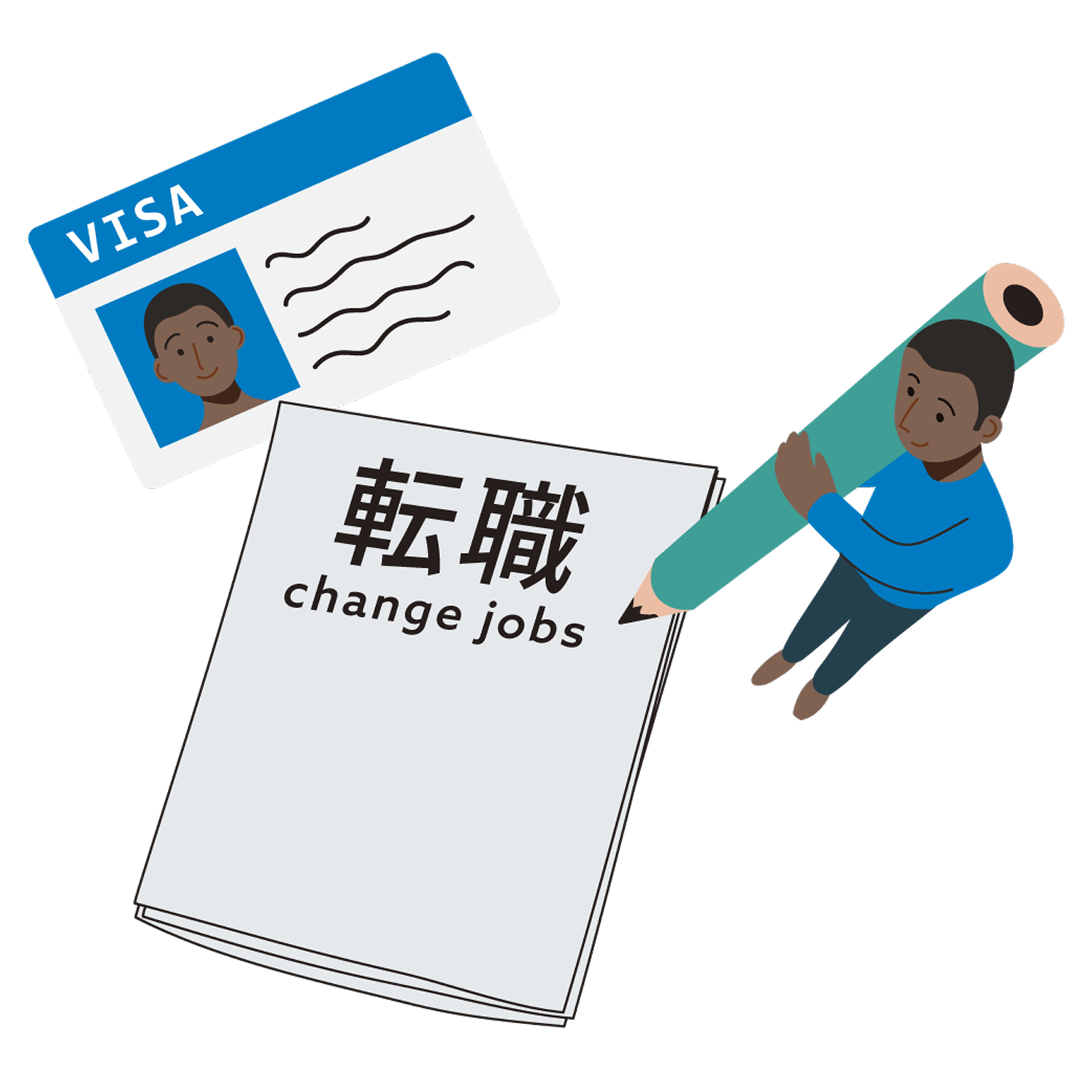
日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、
ビザの更新や変更の手続きが不安など、
日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を
ご紹介していします。
Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。
まずは気軽に相談してください。