
目次
日本で働くなどして生活する外国人は、全員が日本の公的な医療保険制度を利用できます。勤め先で加入する社会保険や、留学生などを対象とする国民健康保険では、万一の病気やけがのときに原則として医療費の70%が支給されるほか、出産などのときに一定額の給付を受けることができます。
ここでは、外国人でも利用できる公的医療保険の基本から、会社員・学生・自営業者それぞれの加入方法、家族の取り扱い、そして実生活で役立つ制度(高額療養費や傷病手当金、出産育児一時金、脱退一時金)を整理します。
日本の健康保険は、病院や薬局で必要になる費用につき、原則として70%まで負担してもらえる医療保険制度(Health Care Insurance System)です。国籍や滞在目的とは関係なく、原則として3か月より長く日本に住む予定がある人であれば、いずれかの健康保険に全員加入しなければなりません。
ここでは、日本に住む場合の健康保険の種類や、外国人が加入を義務づけられる場合、ほかに健康保険で受けられるサービスについてチェックしましょう。
日本に3か月を超えて滞在する予定がある外国人は、原則として全員が健康保険に入ります。このあと解説する「社会保険」に加入できる条件を満たさない人は、すでに紹介したように、住んでいる市区町村で国民健康保険に加入することになります。
日本の公的医療保険には、大きく分けて2つの種類があります。どちらに加入するかは、あなたの働き方や状況によって決まります。
日本の会社で働く人には、一定の要件を満たすときは、会社の健康保険に加入させてもらえます。このような働く人向けの健康保険は「社会保険」と呼ばれ、次の条件に当てはまる場合はアルバイトやパートであっても加入します。
留学生や退職した人は、住んでいる地域の市町村役場で「国民健康保険」に入ります。自分でビジネスを営む人や、会社で勤めていても社会保険に加入する条件を満たせない人(働く時間が短い人など)も、国民健康保険で医療サービスを受けられます。
気を0つけたいのは、勤務先の社会保険に加入していた人が退職した場合です。このとき、何もしなくても国民健康保険に加入するわけではなく、自分でマイナンバーカードや役所の窓口を利用して保険を切り替える必要があります。
社会保険(勤め先の会社で入れてもらえる健康保険制度)のメリットのひとつに、一定の条件を満たす家族を「被扶養者」として一緒に保険に入れる「扶養」の制度があります。被扶養者となった家族は、自分で保険料を支払うことなく保険のサービスを受けられます。
家族を扶養に入れるためには、その家族が扶養する人の収入によって生活している必要があります。具体的には、ここにある条件を両方とも満たすことが求められます。
ただし、家族の収入が扶養する人の収入の半分以上であっても、決して収入が上回ることがないときには、生活状況から特別に被扶養者として認められるケースもあります。
被扶養者になれるのは、市町村ごとにある「住民票」に記載のある家族に限られるのが基本です。ただし、やむを得ない理由で一時的に海外で暮らす家族は、日本で住民として登録されていなくても「海外特例」として被扶養者になれる可能性があります。
ここで紹介する特例を申請する際には、留学先の学生証やビザなど、海外に住む理由や期間を証明する書類の提出が必要です。
※参考:健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)
2つの保険制度には、手続きの場所や保険料の支払い方、家族の加入などで違いがあります。以下の表で、主な違いを確認してみましょう。
| 比較項目 | 会社で入る健康保険 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 加入対象 | 会社員など | 自営業者、学生、無職の人など |
| 手続きの場所 | 勤務先の会社 | 住んでいる市区町村の役所 |
| 保険料の負担 | 会社と本人が半分ずつ負担 | 全額を本人が負担 |
| 扶養の考え方 | あり(条件を満たす家族を扶養に入れられる) | なし(加入者一人ひとりが被保険者) |
| 傷病手当金 | あり(病気やケガで休業した際の所得保障) | なし(一部組合では任意で制度あり) |
日本の健康保険は、病院に行ったときの医療費が安くなるだけではありません。高額な医療費がかかったときや、日本で子どもが生まれたときなど、さまざまな場面で生活をサポートしてくれます。
ここでは、健康保険に加入している外国人が利用できる、知っておくと便利なサービスを紹介します。
病院やクリニック、薬局の窓口で健康保険証を提示することで、自分で支払う医療費はかかった費用の原則30%になります。
たとえば、治療費が10,000円だった場合、窓口で支払うのは3,000円で済みます。残りの70%は健康保険の負担となるため、医療費の心配を大きく減らすことができます。
手術や入院などで1か月の医療費が非常に高額になってしまった場合でも、健康保険に加入する人が負担する金額は「高額療養費制度」で上限が定められています。
この上限額を超えて支払った医療費は、後から申請することでお金が戻ってきます。
日本で子どもが生まれた時には、加入している健康保険で「出産育児一時金」を受け取れます。支給額は、赤ちゃん一人につき50万円が基本で、出産にかかる費用を補助してくれます。妊娠がわかったら、この制度について確認しておくと、安心して出産準備を進めることができるでしょう。
日本の健康保険は、高齢で退職したときや障がいを負ったときの年金制度と一体になっています。日本の年金制度にも加入して6か月以上加入していた外国人が、日本から完全に出国する場合、それまでに支払った年金保険料の一部を「脱退一時金」として受け取ることができます。
※参考:脱退一時金の制度(日本年金機構)
仕事以外の原因による病気やケガで会社を休まなければならなくなった時、生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。連続して3日間休んだ後の4日目から、給与が支払われない期間について、給与のおおよそ3分の2の金額を最も長くて1年6か月にわたって受け取れます。
日本で生活を始めるにあたり、健康保険の加入は法律で定められた義務であり、避けては通れない手続きです。しかし、手続きの方法は、自分の働き方や状況によって異なります。会社で働く場合と、学生や自営業者として生活する場合では、手続きの窓口や流れが変わるのです。
ここでは、それぞれのケースに応じた健康保険の加入方法について、具体的に解説していきます。
※以下、参考:外国人従業員を雇用したときの手続き(日本年金機構)
働いている人の健康保険(社会保険)の加入手続きは、すべて勤め先の会社が行ってくれるのがふつうです。自分で役所などに行く必要はなく、会社の担当者の案内に沿って書類を作るだけで手続きは完了します。
■手続きの流れと準備する書類
……入社後、会社の担当者から健康保険に加入するための案内があります。その際、あなたの在留資格や就労資格を確認するため、「在留カード」や「パスポート」のコピーの提出を求められるのが一般的です。会社によっては、アルバイトなどで働く場合に「資格外活動許可書」のコピーが必要になることもあります。会社がこれらの情報をもとに日本年金機構へ届け出を行います。
■保険証はいつ届く?
……勤め先の会社による手続きが完了してから、通常1〜2週間ほどで健康保険証をもらえます。健康保険証を受け取るときは、勤め先経由となります。
会社の健康保険に加入しない学生や自営業者、フリーランスとして活動する人は、自分で住んでいる地域の役所へ行き、国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
■手続きの期限と場所
……日本で居住を開始した日(住民票を作成した日)や、前の会社の健康保険を辞めた日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所の窓口で手続きをしてください。
■手続きに必要なものと保険証の受け取り
……手続きには、パスポートと在留カード、そして日本で付与されたマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。書類に不備がなければ、国民健康保険の保険証は原則としてその日のうちに窓口で交付されます。
健康保険のさまざまなサービスを受けるためには、毎月決められた保険料を支払う必要があります。この保険料は、日本の医療制度を支えるための大切な費用です。
ただし、保険料の金額や支払い方法は、あなたが加入している保険の種類によって異なります。ここでは、それぞれの保険料がどのように決まり、どうやって支払うのかを解説します。
会社の健康保険(社会保険)の保険料は、毎月の給与を一定の区切りで分けた「標準報酬月額」に、決められた「保険料率」を掛けて金額が決まります。
算出された保険料は、会社と半分ずつ負担するのが大きな特徴です。会社が半分を負担してくれるため、個人の負担が軽くなります。
社会保険に加入する人が支払う分の保険料は、毎月の給与から天引きされます。そのため、自分で銀行などに行って支払う必要はありません。
国民健康保険の保険料は、住んでいる市区町村が、前年の所得(収入)などをもとに計算します。前年の日本での所得や、世帯に加入者が何人いるかなどによって、年間の保険料が決まります。そのため、所得が少ない学生などは、保険料が安くなる場合があります。
国民健康保険に加入する場合の保険料の支払いは、市区町村から送られてくる「納付書」を使って、コンビニエンスストアや銀行、郵便局で自分で支払います。
銀行口座からの自動引き落とし(口座振替)の手続きをすれば、支払い忘れを防ぐことができて便利です。
健康保険の手続きや利用方法について、外国人の方からよく寄せられる質問があります。ここでは、特に多くの方が疑問に思う点について、わかりやすく答えます。
A. やむを得ない理由で、保険証が手元に届く前に病院に行かなければならない場合、その場では医療費の全額(100%)を支払う必要があります。後日、新しい保険証と病院の領収書を保険の窓口(会社や役所)や病院に持っていくことで、自己負担分を引いた金額を返してもらえます。
また、会社に依頼すれば、保険証の代わりとして使える「健康保険被保険者資格証明書」を一時的に発行してもらえることもあります。
A. 保険料を支払わずに滞納してしまうと、まず役所から支払いを促す「督促状」が届き、延滞金を請求されることがあります。滞納が続くと、保険証の有効期限が短くなったり、保険証が使えなくなり医療費が全額自己負担になったりする場合があります。
さらに、公的な義務を果たしていないとみなされ、将来のビザの更新(在留期間の更新)で不利になる可能性もあるため、保険料は必ず期限内に支払いましょう。
日本の健康保険(公的な医療保険制度)は、医療費を原則として70%まで支給してくれるしくみなどにより、万一の病気やけがのときの負担を大きく減らしてくれます。注意したいのは、留学生などが加入する国民健康保険の場合、保険料の支払いなどの手続きについて自分で行わなければならない点です。
滞在する国の公的なサービスの内容は、その国で快適に生活できるかどうかにかかわる重要なものです。行政書士法人Luxentでは、日本での生活に必要な情報や、知っておくと役立つ情報をお届けしています。
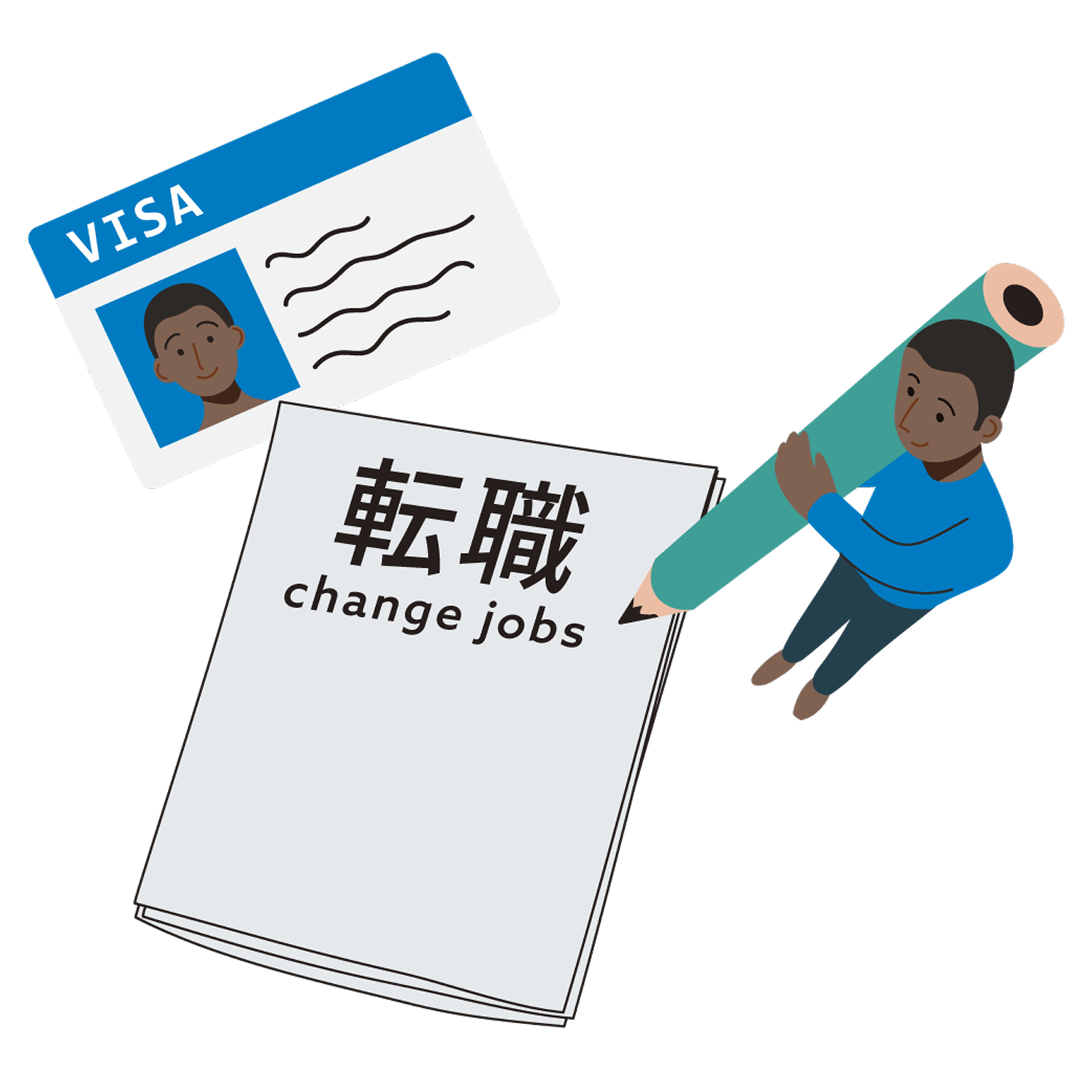
日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、
ビザの更新や変更の手続きが不安など、
日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を
ご紹介していします。
Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。
まずは気軽に相談してください。