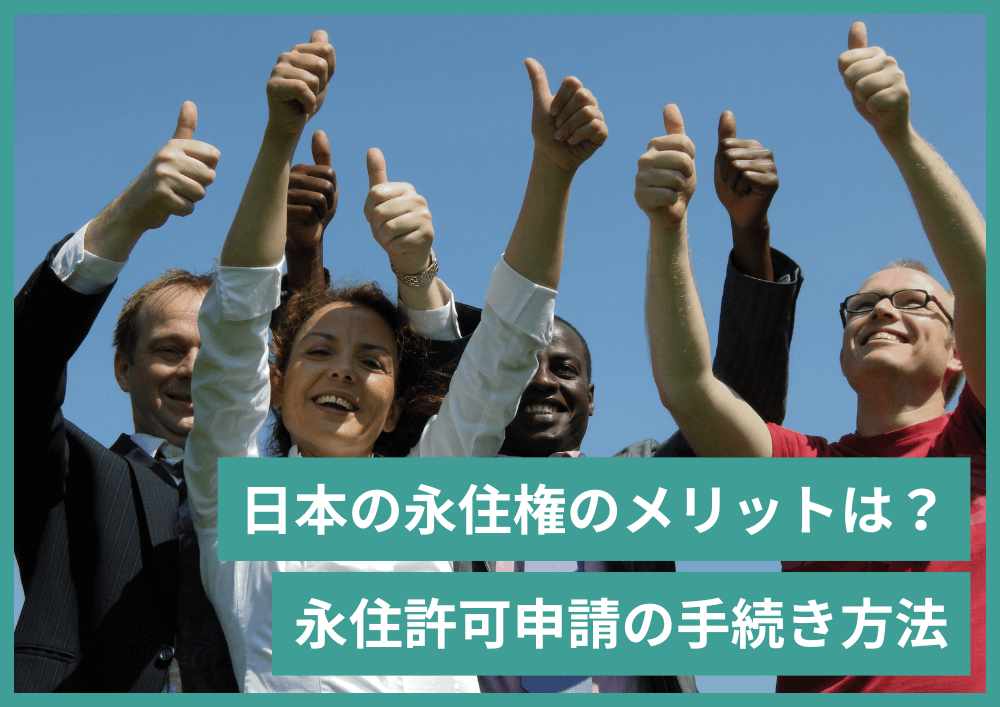
目次
原則として10年以上にわたり日本で生活し、これからもずっと暮らしたいと思う人は、永住権(在留資格「永住者」)をもらえる可能性があります。一定の要件に当てはまれば、5年程度で申請できることもあります。
永住者ビザのメリットは、在留期間の更新がいらなくなる点や、退職や日本人配偶者との離婚を経ても安心して日本にいられる点です。ここでは、日本の永住権の基本から申請方法まで解説します。
日本の永住者ビザは「永住許可」と呼ばれ、とくに活動を指定されることなく日本で長く暮らすための特別な在留資格(ビザ)です。ここでは、永住許可の基本を押さえましょう。
在留資格のひとつ「永住者」とは、日本に暮らす外国人のためのもので、海外に住む日本の在留資格のない外国人が申請をすることはできません。よく似た言葉に「特別永住者」がありますが、これは戦前から日本にいる人やその子どもたちを対象とする別の在留資格です。
永住許可を得て、在留資格が「永住者」になると、日本にいられる期間を新しく得る手続き(在留期間更新許可)を行うことなく、無期限で滞在することができます。働き方や勤め先の業種、職種も制限を受けません。公序良俗(=社会の秩序や道徳)に反しない限り、どんな仕事をしてもかまわないとされます。
「永住者」と「帰化」は、日本で長期的に生活できる点は同じですが、その内容は大きく異なります。簡単に違いを示すと次のとおりです。
永住者は元の国のパスポートを使い続けますが、帰化した場合は日本のパスポートを持つことになります。選挙権が与えられたり、親族関係を公的に証明する「戸籍」が作成されたりするのは、帰化した場合のみです。
在留資格には「永住者」のほかに「定住者」もあります。永住者と定住者で共通するのは活動に制限がない点で、日本にいられる期間の更新有無は異なります。
すでに紹介したとおり永住者は在留期間の更新を必要としませんが、定住者は在留期間が決まっていて更新が必要です。
対象となる人も異なります。定住者は、主に日系人やその配偶者、日本人との間に生まれた子どものほか、難民認定を受けた人など、特別な事情を持つ外国人が対象です。一方の永住者は、もともと長く日本に住んでいる・長く勤めている人が対象となります。
今までも長く日本で暮らし、これからも日本で生活していこうとする人は、積極的に永住許可をもらうことを検討しましょう。永住者ビザのメリットとして、次の5つが挙げられます。
永住許可が下りると、在留期間を更新するために書類を集めたり、不許可になるかもと不安になったりすることがなくなるのは、精神的に大きなメリットです。
※外国人が常に携帯する必要のある「在留カード」は、永住者ビザがあっても有効期間内の更新手続きが必要です。
永住権を持つと、日本社会でより深く信用されるようになります。多くの人がメリットだと感じるのは、自分の家や自家用車を買えるようになることです。
不動産や自動車といった高額な買い物では、銀行からお金を借りなくてはならないのがふつうです。お金を借りるための「住宅ローン」や「自動車ローン」などの契約を外国籍の人が行うとき、多くの場合、永住権があることが条件となります。
自分が永住者であることは、家族にとっても大きなメリットがあります。配偶者や、日本にいるあいだ配偶者との間にもうけた子どもは「永住者の配偶者等」という種類の在留資格がもらえるためです。
在留資格「永住者の配偶者等」も、永住者と同じく、働き方や勤め先に制限がありません。就学中の子どもは、大学や専門学校へ自由に通うことができます。さらに「永住者の配偶者等」から「永住者」への移行もしやすくなります。
永住者ビザを持っていれば、生活環境が大きく変わるようなライフイベントがあったときも安心です。退職や失業、離婚などによって在留資格の目的が果たせなくなっても、在留資格の種類を変更するなどの手続きを経ることなく日本にいられます。
永住許可を持つと、一時帰国でもメリットがあります。日本に戻ってくるときのため事前にもらう許可(再入国許可)につき、原則として最長期間である5年が認められるようになります。
永住者ビザの申請(永住許可申請)には、誰もが満たす必要のある基本的な条件と、日本での滞在年数に関する条件があります。ここでは、永住許可を得るために必要な条件を3つのパートに分けて詳しく解説します。
※以下、参考:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
永住許可をもらうには、どのような人であれ、ここから説明する3つの条件をすべて満たさなくてはなりません。日本で安定した生活を営んでいる人であれば心配しなくていい項目ですが、念のためチェックしておきましょう。
第一に、これまでの日本での暮らしで法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることなく過ごしてきたことが求められます。近隣の人や職場とのあいだで大きなトラブルを起こすことなく過ごしていれば、基本的には問題ありません。交通ルール違反などにも注意をしましょう。
第二に、日本で安定した生活を続けられるくらいの収入や資産を持っていることが求められます。具体的には、下記のような条件を満たさなくてはなりません。
なお、扶養家族(自分の収入で暮らしてもらっている家族)がいる場合は、さらに高い収入が必要です。しかし、家族がいる人の収入は家族をひとつとして世帯単位で判断されるため、働いている配偶者などの収入との合算で考えることが大事です。
第三に、永住することが「日本にとって社会の利益になる」と認められる必要があります。具体的には、下記の条件をすべて満たしていることが求められます。
永住許可の原則的な条件として、「続けて10年以上」日本に在留していることが必要です。これは、途中で長期間日本を離れることなく、生活の基盤が日本にある状態を指します。
さらに、この10年間のうち「直近の5年以上」は「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」といった就労ビザ(働くためのビザ)、または「日本人の配偶者等」や「定住者」といった居住系ビザ(日本で暮らすことが目的のビザ)で在留している必要があります。
注意点として「留学」や「技能実習」、「特定技能1号」の在留資格で日本に滞在していた期間は、この「10年」の在留期間には含まれますが、「5年」の就労期間にはカウントされません。
原則10年の在留が必要ですが、以下に該当する場合は、特例として10年未満の滞在でも永住申請が認められることがあります。
■日本人や永住者と結婚している場合
……実態のある婚姻生活が3年以上続いており、かつ直近1年以上、続けて日本で暮らしている場合に許可の条件を満たします。
■日本人や永住者の子どもの場合
……実の子どもでも養子でも、1年以上継続して日本に在住していれば許可の条件を満たします。
■定住者の場合
……在留資格「定住者」で5年以上継続して日本に在住している場合に許可の条件を満たします
■高度専門職ポイントが70点以上ある場合
……在留資格「高度専門職」で3年以上継続して日本に在住していれば許可の条件を満たします。
■高度専門職ポイントが80点以上ある場合
……在留資格「高度専門職」で1年以上継続して日本に在住していれば許可の条件を満たします。
■日本への貢献が認められる場合
……スポーツ、文化芸術、科学技術などの分野で国際的に高い評価を受けたり、日本の社会や経済に大きく貢献したと認められたりした人は、5年の在留で申請できる場合があります。
永住権の条件を満たしていることがわかったら、申請の準備を進めましょう。ここでは、申請の準備から新しい在留カードを受け取るまでの具体的な流れを解説します。
永住許可申請では、指定された「永住許可申請書」のほかに、許可の条件を満たすことを証明する書類が必要です。現在持っている在留資格や、あなたの状況によって必要書類は異なります。ここでは一般的な書類をリストアップしますが、必ず出入国在留管理庁(入管)のウェブサイトでご自身のケースに合った最新の情報を確認してください。
※参考:【就労資格】提出書類一覧および【就労資格以外】提出書類一覧(出入国在留管理庁)
永住許可の申請にあたっては、基本的に下記の書類が必要です。
今の在留資格の目的となる活動を証明できるものとして必要な書類は、働き方によって異なります。基本的には、下にある書類のいずれかを用意します。用意できない場合は、勤め先の会社と協力して職業に関する説明書を作り、その証明になる書類を添える必要があります。
また、各種税金の証明書とは、所得税(収入に応じて毎年支払う税金)などのさまざまな種類のものが必要です。必要とされるのは、次の種類の税金に関する納税証明書です。
永住許可申請をするときに許可されている在留資格の種類によっては、審査のため追加で書類を必要とします。「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格や、「高度外国人材」として日本で働いている人などです。
■日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
……結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、自分で作成した親族一覧表など
■高度外国人材として日本で働く人
……高度専門職ポイント計算表、高度専門職ポイント計算結果通知書、ポイント計算の根拠となる証明書など
永住許可申請をする人の収入が基準を満たすか、また適切なタイミングに税金をきちんと納めているのかを証明するため、原則として下にある書類をすべて提出しなければなりません。課税証明書と納税証明書は住んでいる地域の市町村役場で取得でき、基本的には直近5年分を必要とします。
なお、次のどちらかの条件に当てはまる人の住民税の課税証明書と納税証明書は、直近1年分だけで構いません。
また、次のどちらかの条件に当てはまる人の住民税の課税証明書や納税証明書は、直近3年分で構わないとされます。
日本の社会保険(健康保険や国民年金)についても、加入していることや、支払い状況についてわかる書類が必要です。永住許可申請では、原則として直近2年分、下記の書類が必要です。
■年金の加入状況や支払い状況がわかるもの
……日本の年金事務所からもらえる「ねんきん定期便」や、被保険者記録照会回答票、納入証明書など
■健康保険の加入状況や支払い状況がわかるもの
……健康保険証の写し(マイナ保険証にしている場合はマイナポータルで印刷した資格証明書)、保険料の納付証明書など
※2025年7月現在、カード型もしくは紙でできた健康保険証を新しく発行してもらうことはできません。健康保険が変わったり新しく加入したりした場合は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」となります。
なお、次のどちらかにあてはまる人は、永住許可申請のときの社会保険に関する書類について直近1年分で構わないとされます。
永住申請には、日本人もしくは永住者の身元保証人が必要です。保証人になってくれる人に「身元保証書」を作ってもらい、運転免許証などの身分を証明するものを用意してもらいましょう。配偶者がいる場合は通常配偶者が身元保証人となります。
■身元保証書見本
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002536.pdf
2021年10月1日以降は、永住許可申請から結果が届くまでのあいだの注意事項について「了解しました」という内容の了解書も提出しなければなりません。注意事項とは、勤め先や家族の状況、税金などの支払い状況などについて変化があった場合、必ず出入国在留管理局(入管)に進んで知らせるというものです。
■了解書見本
https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
すべての書類が揃ったら、住んでいる地域を管轄する入管(さがすときはこちら)で申請します。申請できるのは本人であり、18歳未満の子どもについては親(法定代理人)が申請することも可能です。そのほか、行政書士や弁護士などの専門家に申請取次を依頼することも可能です。
申請するときは、次のものを提示するようにしましょう。
申請時には手数料はかかりません。 申請後は、審査結果が出るのを待つことになります。標準的な審査期間は4か月から6か月とされていますが、実際には半年から1年近くかかることもよくあります。
審査の結果を待っているあいだも、今持っている在留資格で日本にいられる期限(在留期限)が迫っている場合、更新しなければなりません。ほかの在留資格とは取り扱いが異なるため、忘れないように注意しましょう。
審査の結果、無事に永住許可が下りると、入管から許可通知のハガキ(または封書)が届きます。通知書に記載された期間内に、入管の窓口へ行きましょう。入管の窓口では、新しい在留カードをもらうため次のものが必要です。
一度もらった永住許可も、特定の条件に該当した場合は取り消されることがあります。2024年から2025年にかけて、とくに税金などを支払わない人について厳しい対応が取られるようになりました。
無事に日本で永住権を得た後も、次のようなルール違反をしないように注意しましょう。
■意図的に税金や社会保険料を支払わない
……永住許可を得た後に、故意に(わざと)税金や社会保険料を納めない場合、永住許可が取り消されることがあります。これまではこのような規定はありませんでしたが、永住者にも公的義務を果たすことが厳しく求められるようになりました。
■入管法で定められた届出などの義務を守らない
……引っ越しをした際の住居地の届出や、在留カードの有効期間の更新手続きなど、入管法で定められた義務を正当な理由なく行わなかった場合も、取り消しの対象となり得ます。
■うその書類で申請する
……申請時に、嘘の書類を提出したり、事実と異なる内容を記載したりして永住許可を得たことが後から発覚した場合は、許可が取り消される可能性があります。
■1年以上の懲役または禁錮刑に処せられる
……日本国内外で、特定の重大犯罪や1年を超える懲役または禁錮にあたる罪を犯し、有罪判決が確定した場合は、退去強制の対象となり、永住許可も失う可能性があります。
■在留カードの常時携帯義務違反を繰り返す
……在留カードを常に携帯することは法律で定められた義務です。この義務に違反することを繰り返すなど、素行が善良でないと判断された場合も、取り消し理由となり得ます。
永住者ビザ(在留資格「永住者」)は、今後の仕事や生活の自由度が格段に上がり、日本での安定した未来を築くための強力な味方です。収入要件や税金の支払い状況などについて厳しい審査がありますが、ルールを守って安定した生活を築き、これまでの暮らしぶりを証明できるものが揃っていれば大きな心配は無用です。
日本で永住権が取れるか不安な人や、複雑な書類集めや手続きに自信がない人は、一人で悩まず専門家にご相談ください。行政書士法人Luxentは、入管手続きのプロとして、外国人や外国人を受け入れる人々を支援しています。
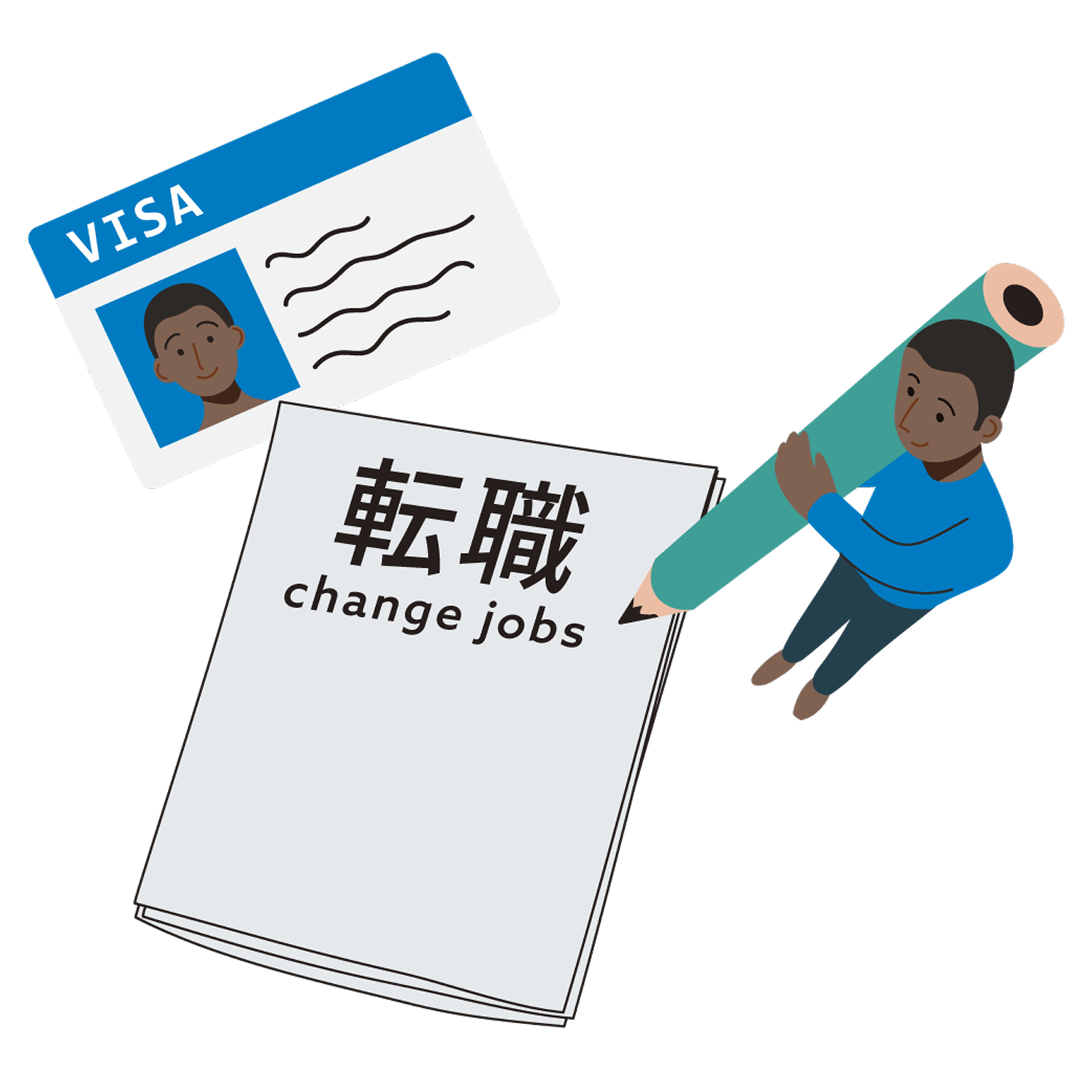
日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、
ビザの更新や変更の手続きが不安など、
日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を
ご紹介していします。
Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。
まずは気軽に相談してください。